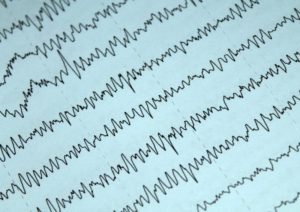目次
マインドフルネスは痛みを減らす

皆さんは、マインドフルネスや瞑想をどんな目的でやっていますか?
ネガティブな感情を減らしポジティブな人生を送るためという方もいれば、集中力を高めるためという方もいるでしょう。
実際どちらも研究で効果が繰り返し検証されていることでもあります[1]。
それに加えて、驚くべきことにマインドフルネスは痛みを減らすということが明らかになってきています。
2020年に痛みの研究で権威ある学術誌、Pain誌に報告された研究を簡単に紹介しましょう[2]。
この研究では、偏頭痛を持つ98名の大人を集め、うち50名はマインドフルネスを行うグループ、残りの48名は偏頭痛を引き起こすストレスについて学ぶグループに割り当てられました。
両者ともに8週間の長期的な訓練となっています。
結果をわかりやすく示しましょう。
まず痛みの程度については
そして改善が見られた人の割合は
と明確な差が見られました。
ちなみに、どちらの指標も統計的に有意な差でした。
これらの結果から、マインドフルネスの訓練は痛みを減らす効果があるのだろうということが示されました。
実際、メタ分析においてもマインドフルネスは慢性疼痛などに効果があることが示されているのです。
それでは、このような効果はどのようなメカニズムで得られているのでしょうか。
研究内容

その点を検討した研究が、先ほどの研究と同じく2020年にPain誌に報告されています[3]。
この研究での疑問点を簡単にいうと、マインドフルネスで痛みが減るのは薬と同じメカニズムなのか?ということでした。
例えば有名な鎮痛剤にモルヒネがあります。
モルヒネは戦争映画などでもよく見られるように、打つと一気に痛みを感じる神経が抑制され、痛みを感じにくくなります。
その強い効果から、手術後の痛み止めなどにも使われるものです。
それだけ強い効果ですので、中毒性もあり乱用はできません。
果たして、マインドフルネスはモルヒネと同じようなメカニズムで痛みを抑制しているのでしょうか。
もしそうだとすると、中毒性や副作用がないか少し心配になりますね。
これを調べるための具体的な研究内容を説明していきましょう。
まずこの研究では60名の参加者を集め、以下の3グループに分けました。
の3グループで、それぞれ20分のセッションを4回行いました。
結果:呼吸への意識は痛みを減らす

その結果はどうだったのかというと、第一にやはり
①マインドフルネスグループと②ゆっくりした呼吸を意識するグループは、熱い刺激に対する痛みが統計的に有意に減少していました。
やはりマインドフルネスが痛みを減らす効果を確認できたんですね。
そして②の呼吸を意識するだけのグループでもその効果が得られたということは、マインドフルネスの中でも呼吸に意識を向けることが痛みを減らすためには重要だということでしょう。
さて、この研究が面白いのはここからです。
結果:内因性オピオイドを抑制しても痛みが減る

少しわかりづらいのですが、この研究ではとある薬によって「内因性オピオイドを抑制する」という実験もしていました。
オピオイドとは要するにモルヒネのようなものですが、内因性オピオイドは私たちの体内で生み出されるモルヒネのようなものです。
いわば天然の痛み止めで、これが体内で出ている時には痛みを感じにくくなります。
これを薬で抑制したということは、痛みを感じやすくなると予想されますね。
この状況で、実験参加者は熱刺激を与えられて痛みを評価しました。
手を熱せられたときにどのぐらい痛かったかを回答するのです。
この実験には2通りの結果が予想されます。
まず第一に、マインドフルネスをした人たちも痛みを強く感じる可能性があります。
この場合、マインドフルネスによる痛みの抑制は内因性オピオイドによる効果であると考えられます。
少しわかりづらいかもしれませんが、第二の可能性も説明します。
第二の可能性は、マインドフルネスをした人たちは内因性オピオイドを抑制した場合でも痛みを感じにくいという可能性です。
この場合、マインドフルネスによる痛みの抑制は内因性オピオイドによる効果ではないと考えられます。
なぜそういえるかを少し説明しましょう。
もしも仮にマインドフルネスが「内因性オピオイドを利用して」痛みを抑えているのだとすると、そもそもの内因性オピオイドが抑制された場合にはその効果が発揮できなくなるからです。
もしも逆にマインドフルネスが「内因性オピオイドを利用せずに」痛みを抑えているのだとすると、仮に内因性オピオイドが抑制されたとしても関係なくその効果が発揮できるはずだからです。
専門用語も多くわかりづらいという方もいるかもしれませんが、その場合はざっと読み流してしまっても大丈夫です。
この辺りが分からなくても結果の部分についてはわかるように説明していきます。
結果どうだったかというと、内因性オピオイドを抑制した場合でも、マインドフルネスグループは痛みを抑えられることが明らかになりました。
ごちゃごちゃとしていますが、要するにマインドフルネスは「内因性オピオイドを介さずに」痛みを抑えていることが強く示唆されました。
言い換えれば、薬物的なメカニズム以外の方法で、マインドフルネスは痛みを抑えているのです。
考察:なぜマインドフルネスで痛みが減るのか

これはとても興味深い結果です。
これまでは、基本的に痛みを抑えようと思ったらモルヒネのような薬物に頼ってきました。
しかし、それとは全く異なるメカニズムでマインドフルネスは痛みを抑える効果があるのです。
ここからは仮説となってしまいますが、マインドフルネスは思考回路を変化させます。
例えば、嫌なことがあってもそれを認め受け入れるように、さまざまな物事をあるがままに受け入れられるようになるのがマインドフルネスです。
そのように思考回路が変わることによって、痛みに対してもネガティブな捉え方をせずに受け入れられるようになるのかもしれません。
結果、痛みを感じにくくなる可能性があります。
思考回路が変わって痛みの感覚が変わるのだとすると、とても興味深いですよね。
思考回路や思考習慣の不思議さを物語っています。
まとめ

さて、今日はマインドフルネスが痛みを抑えるメカニズムについて考えてきました。
内因性オピオイドという鎮痛剤的な化学物質を利用せずとも、マインドフルネスは痛みを抑えるのでしたね。
これはとても面白い結果です。
思考回路や思考習慣の変化によって痛みの感覚までも変化していくのです。
きっと、この変化は痛みだけでなく他の様々な感覚や感情にもみられるのではないでしょうか。
あなたが瞑想やマインドフルネスによって思考回路を変化させれば、それに伴ってあなたの感情や生活にもポジティブな変化が現れるはずです。
ぜひこれからもマインドフルネスな習慣を続けてみてください。
※本記事の内容は、執筆当時の学術論文などの情報から暫定的に解釈したものであり、特定の事実や効果を保証するものではありません。
当記事を読んだ方におすすめの記事はこちら↓
論文レポート:スマホ瞑想アプリの効果が検証される
参考文献
1. Eberth, J., and Sedlmeier, P. (2012). The Effects of Mindfulness Meditation: A Meta-Analysis. Mindfulness (N. Y). 3, 174–189.
2. Seminowicz, D.A., Burrowes, S.A.B., Kearson, A., Zhang, J., Krimmel, S.R., Samawi, L., Furman, A.J., Keaser, M.L., Gould, N.F., Magyari, T., et al. (2020). Enhanced mindfulness-based stress reduction in episodic migraine: A randomized clinical trial with magnetic resonance imaging outcomes. Pain 161, 1837–1846.
3. Wells, R.E., Collier, J., Posey, G., Morgan, A., Auman, T., Strittmatter, B., Magalhaes, R., Adler-Neal, A., McHaffie, J.G., and Zeidan, F. (2020). Attention to breath sensations does not engage endogenous opioids to reduce pain. Pain 161, 1884–1893.