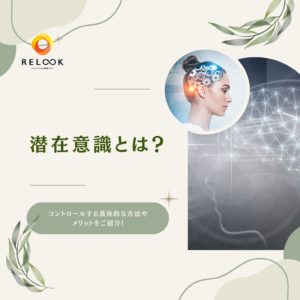メンタルを鍛える方法を知りたい!
そもそもメンタルが強い人ってどんな人?
メンタルを鍛えるためには、マインドフルネス瞑想やアファメーションを生活に取り入れることがおすすめです!
実際に、メンタルが強い人は、日々の生活にマインドフルになる習慣を取り入れていることが分かっています。
ただし、メンタルを鍛えるためには、精神面だけのケアでなく、食生活や運動面での身体的な面からのアプローチも重要です。
そこで本記事では、精神面・身体面からメンタルを鍛える方法をご紹介します。
【この記事を読むと分かること】
メンタルが強い人の5つの特徴
メンタルを鍛える必要性
メンタルを鍛える方法|マインドフルネス瞑想・アファメーション
メンタルを鍛える方法|食生活の見直し
メンタルを鍛える方法|適度な運動
専門家の知見のもとにご紹介します。メンタルを鍛えたい方は、本記事の内容を参考に、生活習慣を見直してみましょう。
目次
メンタルが強い人の5つの特徴
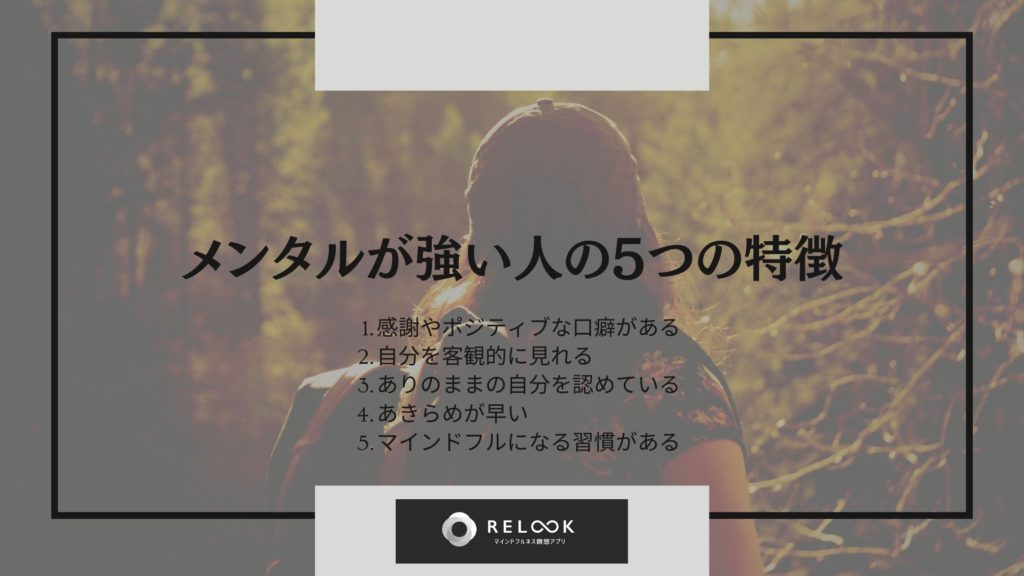
メンタルが強い人の特徴を知ることで、メンタルを鍛える方法が分かります。メンタルが強い人の特徴は以下の5つです。
- 感謝やポジティブな口癖がある
- 自分を客観的に見れる
- ありのままの自分を認めている
- あきらめが早い
- マインドフルになる習慣がある
専門家の知見や実際の研究結果に沿って解説します。
特徴1. 感謝やポジティブな口癖がある

メンタルが強い人は感謝・ポジティブな口癖があります。
「感謝の実践が Well-being に及ぼす影響の研究」では、「ありがとう」という感謝の言葉を1日1回以上3ヶ月継続したところ、ポジティブな感情が生まれ、自分の成長への意欲が高まったとのことです。
また、心理士の佐藤セイ氏によると、メンタルが強い人は「運がいい」「次は〜してみよう」などの口癖もあるとされています。
メンタルを鍛えたい人は、感謝やポジティブな言葉を積極的に使っていきたいですね。アファメーションを実践することで、意識的にポジティブな言葉を使うことができます。
特徴2. 自分を客観的に見れる
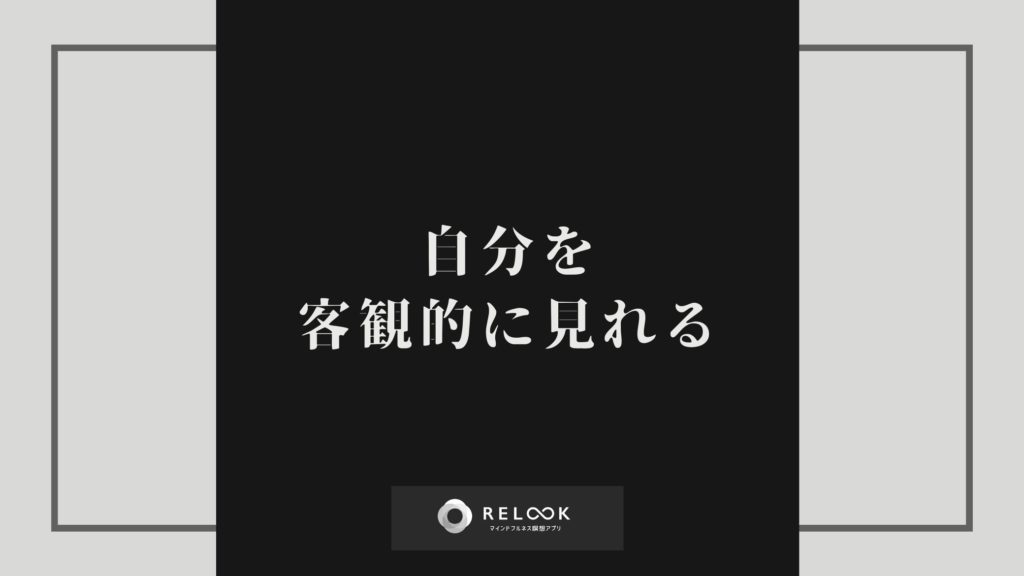
自分を客観的に見れることは、メンタルの強さにつながります。自分を客観的に見れることで、ネガティブな感情と自分をうまく切り離すことができるからです。
精神科医の川野氏も「自分を客観視できないと、ネガティブになりやすくなる」と言っています。
自分がネガティブな思考になったときに、その感情を俯瞰できれば、自分のそのときの思考や感情を落ち着いた気分で受け入れられるようになり、落ち込みにくくなるというわけです。
後ほど詳しい方法をご紹介しますが、自分を客観視する力を育むためには、「メタ認知」を鍛える必要があります。メタ認知を鍛えて自分を客観視できるようになりましょう。
特徴3. ありのままの自分を認めている
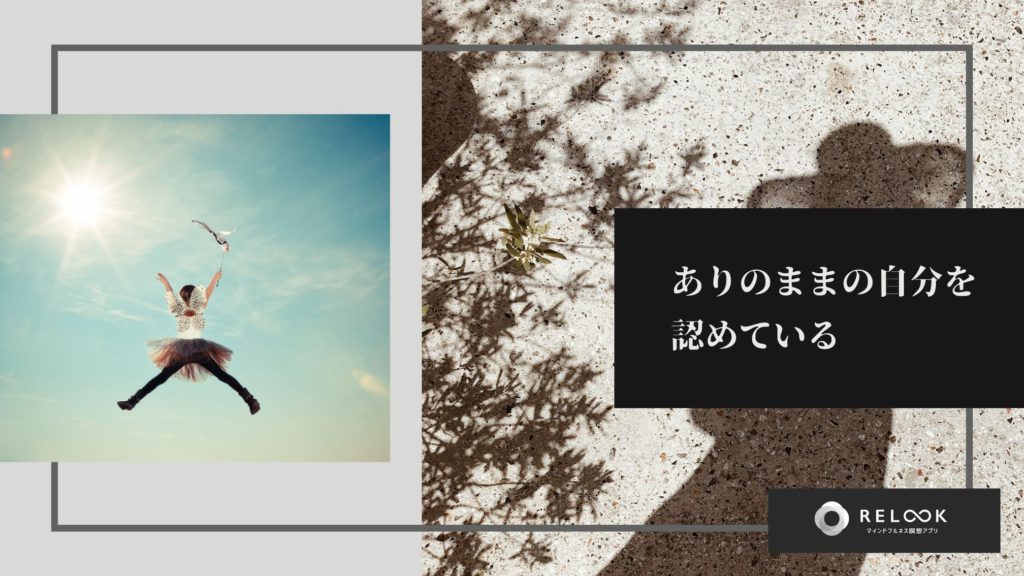
ありのままの自分を認めるのは難しいことですが、メンタルが強い人はこれを実践できています。
実際に、「ポジティブな生き方態度の形成要因に関する検討の研究」によると、ポジティブな生き方をしている人はありのままの自分を認めているという研究結果が示されています。
マインドフルネス瞑想を実践すると、自分のことをありのままに受け入れられるようになります。自分の嫌な面もひっくるめて、「これが私なんだ」と、自分自身を認めてあげられるようになりたいですね。
特徴4. あきらめが早い
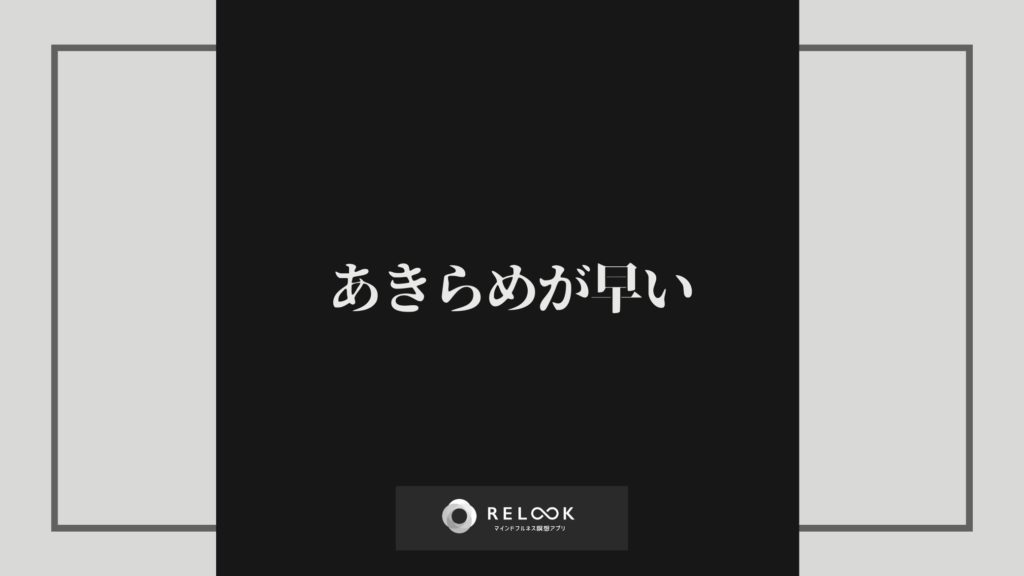
メンタルが強い人はあきらめも早いです。あきらめが早いというのは、うまくいかないことにクヨクヨ悩まず、「まぁいっか」という気持ちで、次のステップに進めるということです。
うまくいかないことにいつまでも縛られていても、何もメリットがないですよね。マインドフルネス瞑想で切り替える力をつけて、メンタルを鍛えましょう。
特徴5. マインドフルになる習慣がある
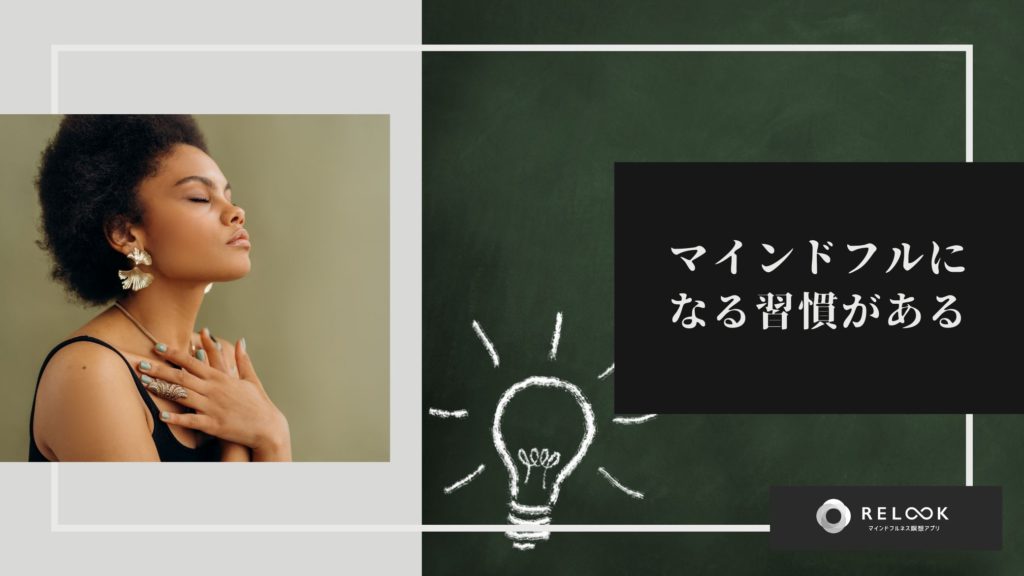
心理士の佐藤セイ氏によると、メンタルが強い人は、マインドフルになる習慣があるとのことです。マインドフルな状態とは、自分自身の「今この瞬間」に注目している状態です。
後ほど詳しくご紹介しますが、マインドフルな状態になるための方法の1つに「マインドフルネス瞑想」があります。そのほかにも「ほめ日記」やアファメーションも効果的です。アファメーションについても後ほどご紹介します。
マインドフルになる習慣を身につけて、メンタルを鍛えていきたいですね。
メンタルを鍛えることの必要性

現代では、特に日本人のメンタルを鍛える必要性があると言われています。その理由は、日本の若者の自殺数が増えていることや、うつ病等の気分障害の総患者数はH8年から20年の12年間の間に2.4倍に増えた点にあります。
メンタルが弱いままだと、最悪な結果を招くだけでなく、これから掴めるはずの幸せやチャンスも逃してしまうかもしれません。
また、医師である武神氏によると、大人のストレスコントロール力が子どものメンタルの強さにも影響すると言及されています。あなた自身の人生・そして子どもの人生がより豊かになるように、メンタルを鍛えていきたいですね。
【関連記事】
メンタルを鍛える方法|メンタルトレーニング

メンタルを鍛える方法を2つご紹介します。
- マインドフルネス瞑想
- アファメーション
それぞれの方法とメンタルとの関係性を説明します。
【関連記事】
メンタルとマインドフルネス瞑想の関係性

マインドフルネス瞑想とは、「今この瞬間」に集中するための瞑想法です。化学的な効果が証明されており、座る・立つ・歩く・食べる瞑想法など、アレンジ方法が多く、生活のさまざまな場面で活用できるため継続しやすいです。
マインドフルネス瞑想とメンタルとの関係は以下の通りです。
- マインドフルネス瞑想の「深い呼吸」がメンタルを鍛える
- マインドフルネス瞑想で鍛える「メタ認知」がメンタルを鍛える
詳しく解説します。
「深い呼吸」がメンタルを鍛える
呼吸とメンタルには深い関わりがあります。怒り・悲しみの感情が強い時には呼吸が浅くなり、リラックスしているときは自然と深い呼吸をしているのを経験したことがある方もいるのではないでしょうか。
実際に、呼吸が深まると副交感神経が優位になってリラックス状態になることがわかっています。逆に、怒りや悲しみの感情が湧いたときには交感神経が優位になり、ストレス状態になるのです。
ストレス状態を回避するためには、マインドフルネス瞑想で呼吸を深めることで効果が見込まれます。
「メタ認知」がメンタルを鍛える
マインドフルネス瞑想をすることで「メタ認知」を鍛えることができます。
先ほども説明したように、メタ認知とは自分を客観視できるようになるもので、主観をなくして自分の感情をありのままに受け入れる行為のことです。
自分を客観視できるようになることで、自分のストレスとうまく付き合う方法がわかるようになります。
ネガティブな感情になりそうになっても、頭の中で冷静に判断できるようになり、感情に振り回されることもなくなるというわけです。
マインドフルネス瞑想の簡単なやり方
雑念が湧きにくく、一番初心者向けのマインドフルネス瞑想法をご紹介します。
【数を数えるマインドフルネス瞑想】
数をカウントすることで雑念を抑え、マインドフルになることをサポートしてくれます。始まりと終わりが明確なのもおすすめです。
- 落ち着ける環境を整える
- 取り組む時間を決めて、アラームをセットしておく
- 息を吸って1、息を吐いて2、息を吸って3、息を吸って4……と10まで数えて進める
- 10なったら1からまた繰り返す
【関連記事】
メンタルとアファメーションの関係性

アファメーションとは、「私は幸せです」「私は仕事で成功しています」などのポジティブな言葉を宣言することで、その状態を引き寄せる方法です。
アファメーションをすることで、潜在意識がポジティブなものに書き換えられ、メンタルも強くなります。
- プラシーボ効果でポジティブだと思い込む
- RASでネガティブ要素をブロックする
下記で詳しく解説します。
プラシーボ効果でポジティブアだと思い込む
アファメーションをすると、プラシーボ効果が発揮されます。プラシーボ効果とは、「〇〇」ができると思い込めば本当にできるという効果です。
実際に「パッケージが味覚に及ぼすプラシーボ効果の研究」で、プラシーボ効果が実証されています。
アファメーションで「私はポジティブです」「私はいつも明るいです」などと、ポジティブな状態を脳に思い込ませることで、本当に理想とする自分に近づけます。
RASでネガティブ要素をブロックする
アファメーションをすると、脳にあるRASという機能が働きます。
RASとは、数ある情報の中から重要なものだけを優先的にピックアップするフィルターのような役割を持ち、赤だけを強く意識すると赤だけがよく目に入るといった機能です。
アファメーションでポジティブなものだけに意識を持つことで、自然とネガティブ要素をブロックできます。ポジティブなものだけに囲まれて、メンタルが強くしましょう。
アファメーションの簡単なやり方
アファメーションを始める流れをご紹介します。
- 環境と姿勢を整える
- 深い呼吸を10回する
- アファメーションを行う
【メンタルを鍛えるアファメーションの文例】
・私は〇〇ができる
・私は強い人間だ
・私は運がいい人間だ
・私は最高な人間だ
・私は大丈夫
など
メンタルを鍛える方法|食生活の見直し

ストレスは心だけでなく身体でも受けており、メンタル不調には心と身体の両方からのアプローチが重要です。
今までは心の鍛え方を説明してきましたが、食生活を見直して、ストレスに強い身体作りにも励みましょう。
『食べる順番健康法―好きなものをガマンしないでいい!』の著書である公認心理士の大久保氏の知見をもとに解説します。ストレスに強い身体になれる食品は以下の通りです。
- タンパク質
- 塩分
- 色とりどりの野菜
- 摂りすぎに注意したい食品
- カフェインの強い飲み物
- 甘い食べ物
- 炭水化物
とりすぎに注意したい食材も合わせてご紹介します。
タンパク質

タンパク質には、ストレス防御ホルモンを作る成分があります。ニンニクやスパイスの効いた「スタミナ料理」である肉や魚料理などが特におすすめです。
大豆製品や卵など、日常的に摂取しやすいものも食事に取り入れやすいです。鶏がらスープや豚スープなどもタンパク質を摂取できます。
塩分

人は強いストレスを受けると、身体がナトリウムをたもてなくなります。あまりにもナトリウムが不足すると、疲労感・頭痛・意識障害など、さまざまな心配な症状が出てしまうのです。
ナトリウム摂取には、手軽に飲めるインスタント味噌汁がおすすめです。ただし、塩分制限を受けている方はお医者さんに相談してください。
色とりどりの野菜

ビタミンには、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」を作るために必要な成分や、ストレスによって増加する「活性酸素」を抑える働きをする成分などが含まれています。
色とりどりの野菜は、ビタミンが豊富なのでおすすめです。特に意識したいビタミンはビタミンA・ビタミンB群・ビタミンC・ビタミンEの4つです。
ビタミンを十分に摂取して、ストレス耐性力を高めましょう。
摂りすぎに注意したい食品

ストレスを感じているときに摂りすぎに注意したい食品は以下の3つです。
- カフェインの強い飲み物
- 甘いもの
- 炭水化物
カフェインは一時的な疲労回復効果はありますが、摂りすぎると逆に疲れやすくなります。
メンタルの不良にもつながるので飲み過ぎには気をつけましょう。甘いものはストレスがたまると食べたくなりますが、食べ過ぎには要注意です。甘いものも疲れやすさを増します。
炭水化物も甘いものと同様の影響があるので、摂りすぎには気をつけましょう。
メンタルを鍛える方法|適度な運動

メンタルを鍛える方法の1つに適度な運動も必要です。運動がメンタルに与える効果やおすすめの運動法をご紹介します。
- ストレス発散になる
- 生活リズムが安定する
- 自律神経が強くなる
- おすすめの運動
以下で詳しく解説します。
ストレス発散になる
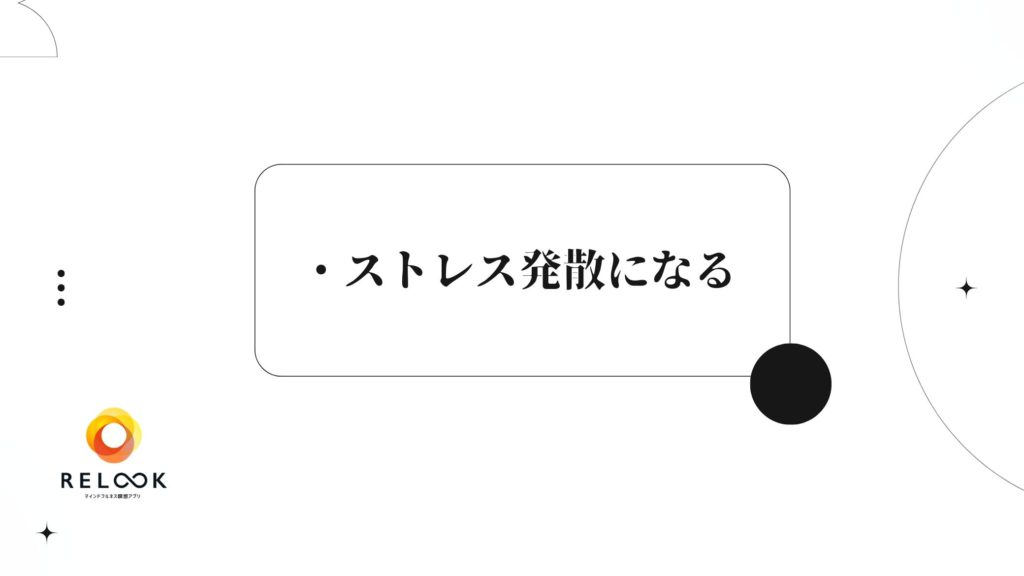
厚生労働省の「健康づくりのための身体活動基準2013」によると、運動はストレス発散や気分転換になり、メンタルヘルスにも良い効果をもたらすとされています。
日常的に運動を取り入れて、ストレス発散していきたいですね。
生活リズムが安定する
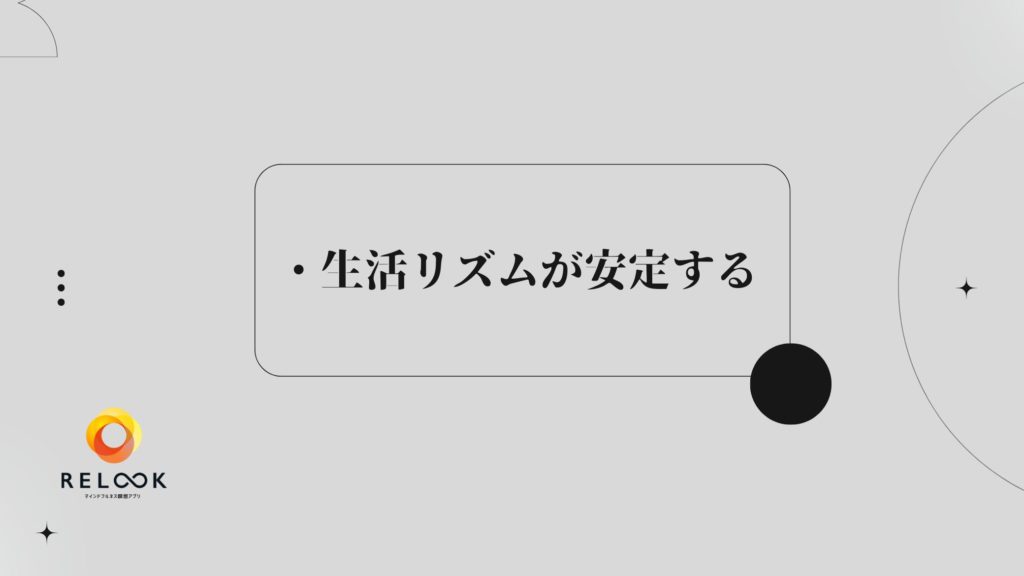
運動をすると適度な疲れを感じるとともに代謝もあがります。代謝があがると、脳への血液量が増加するため、自律神経が整い入眠しやすくなるのです。
朝も起きやすくなり、生活リズムが安定します。快適な睡眠にはストレス解消効果もあります。
自律神経が強くなる
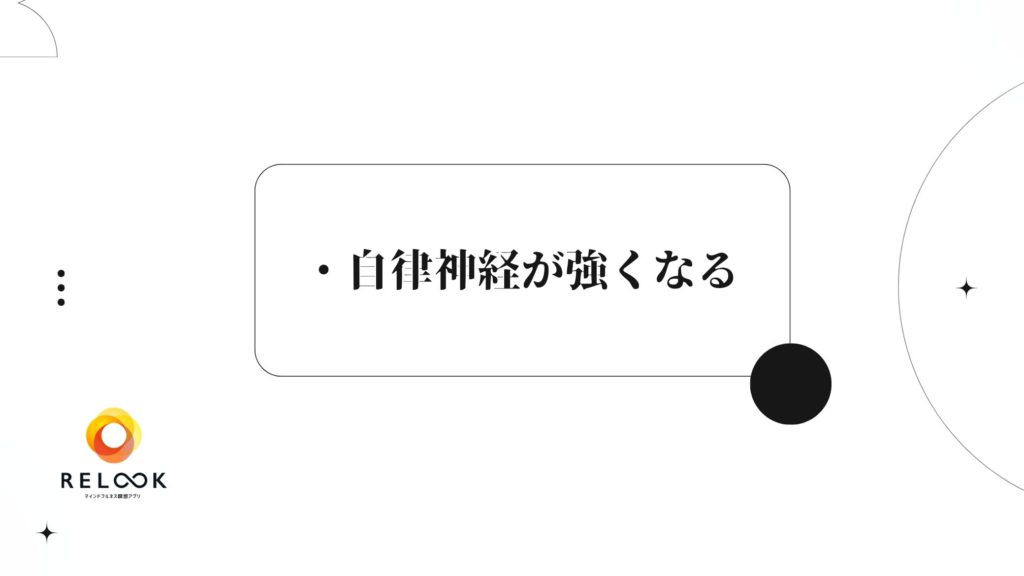
適度な運動をすることにより、自律神経のバランスが整います。運動時には交感神経が優位になり、運度後には副交感神経が優位になるのが一般的な状態です。
自律神経のバランスが崩れると、イライラ・不安・不眠・情緒不安定などの症状がでます。自律神経とメンタルには強い結びつきがあるため、適度な運動を取り入れて、自律神経を整えましょう。
おすすめの運動
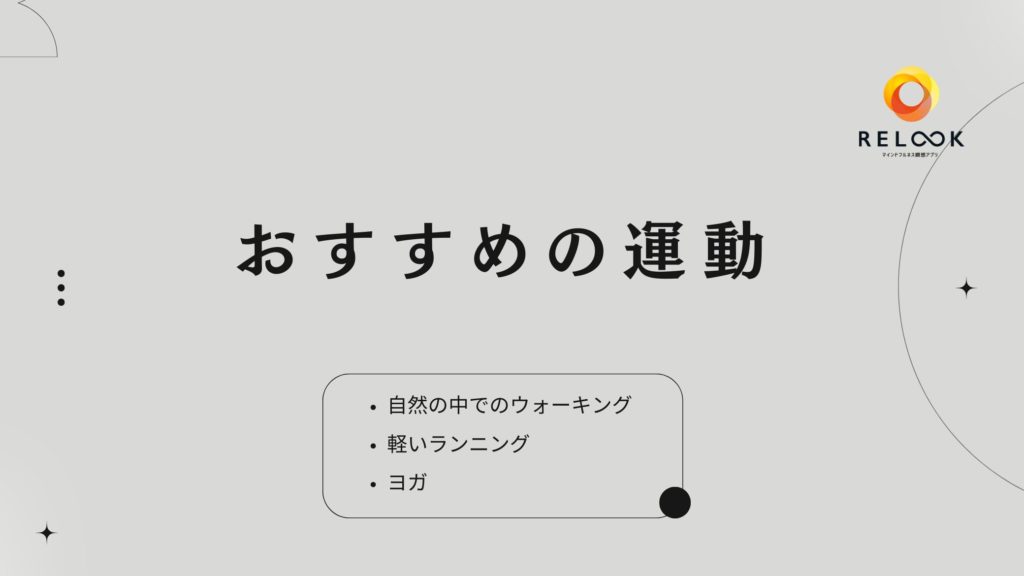
メンタルを鍛えるためにおすすめの運動をご紹介します。
- 自然の中でのウォーキング
- 軽いランニング
- ヨガ
1日15分〜20分程度の運動がおすすめです。自然の中での運動や腹式呼吸を意識できるヨガもストレス解消に効果があります。ぜひ試してみてください。
まとめ
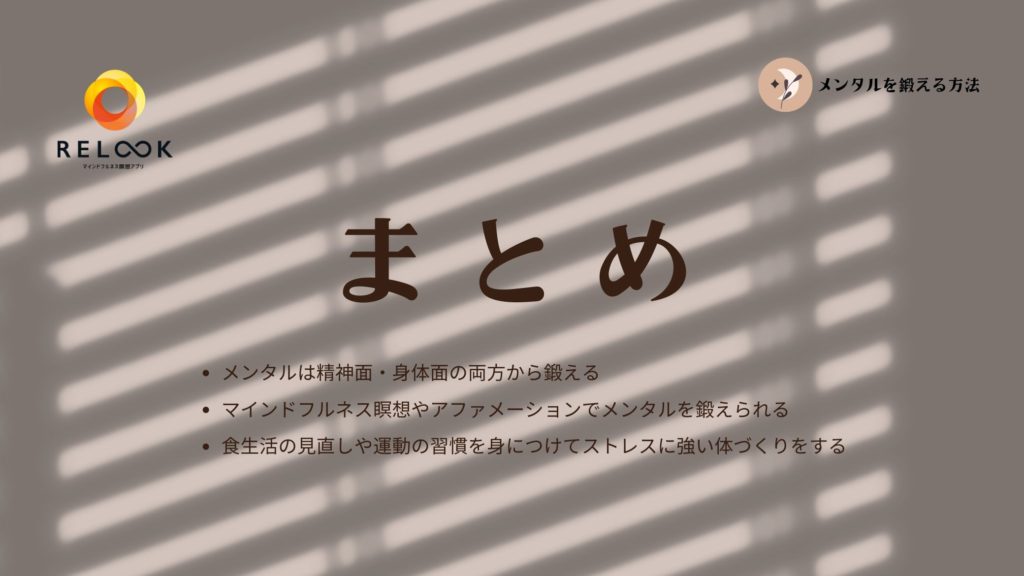
精神面・身体面の両方からメンタルを鍛える方法をご紹介しました。もう一度、メンタルを鍛えるためのポイントを復習しましょう。
- メンタルは精神面・身体面の両方から鍛える
- マインドフルネス瞑想やアファメーションでメンタルを鍛えられる
- 食生活の見直しや運動の習慣を身につけてストレスに強い体づくりをする
上記ポイントをもとに、早速生活習慣を見直してみましょう!
マインドフルネス瞑想やアファメーションを詳しく知りたい方は、関連記事もご覧ください。
【関連記事】